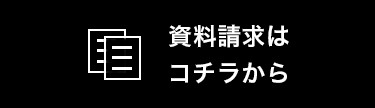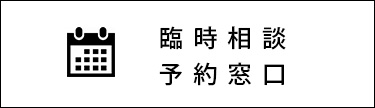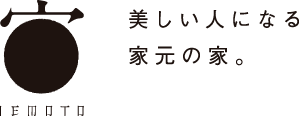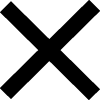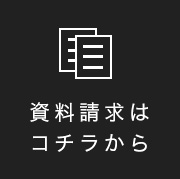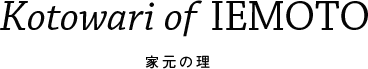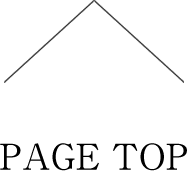2018.05.09
梅雨の時期 お家にカビが発生した時の対処方
こんにちは。
もうすぐ、梅雨の時期ですね。
雨の日が多く
すっきりとした晴れ間が恋しくなる梅雨…
洗濯物が乾かないのに
雨に濡れて着替えれば洗い物は増えるばかり
家事をするものにとっては非常に憂鬱な期間ですね。
そして、ジメジメとした空気で
この時期に発生しやすくなるのが
「カビ」
本日は、「カビ」が発生した場合の
掃除方法・対処方をご紹介します!
まずはカビが発生する状況と原因
カビは
「じめじめとした湿気(湿度70%以上)」と
ホコリ・人のアカなどの「汚れ」
「気温が25~30度」の条件が整うとどんどん増殖します。
場所別の掃除方法・対処方法
1.壁紙に発生したカビ
壁紙に発生したカビは
アルコール(消毒用エタノール)で落とします。
まずは壁紙の下に新聞紙を敷きます。
カビに向けて「消毒用エタノール」を
入れた霧吹きを吹きかけます。
すぐに乾くのですが、その部分を
固く絞った雑巾で下の新聞紙に向けて拭き落とします。
これを3~4回繰り返します。
エタノールでカビ菌は死滅しますが
黒いシミは残ってしまいます。
この「黒」はカビが持つ色素で
大変強力なしつこさがあります
すでにカビは死んでいても、色素だけは残ってしまうのです。
そこで重曹を使って黒いシミを取り去ってしまいましょう。
重曹に数滴の水を含ませて
トロトロにします。
ビニール手袋をした指にそれをつけて
直接壁に塗り付けます。
シミが濃い場合や数が多い場合は
たくさん塗り付けてから
ラップをして10~20分ほど放置して
その後拭き取ります。
状態によって多少とれにくいことも
ありますが繰り返すとほぼ取れるはずです。
薄手の壁紙の場合は
つけたままにすると壁紙が浮いてきてしまうので
数分間放置して拭きとることを
時間の間隔を空けながらやってみてください
2.畳に発生したカビ
畳に発生したカビを落とす際には
まず窓を開けて換気をしながら行いましょう。
消毒用アルコール(エタノール)を
スプレー式容器に入れて
カビ全体に吹きつけます。
そのまま15分ほど放置します。
小分け容器に入れた消毒用アルコールに
浸したブラシで畳の目に沿ってカビをかき出します。
かき出したカビをすくって
小分け容器に入れた消毒用アルコールの中で洗います。
畳についているカビが取れるまで繰り返します。
カビが取れたら
消毒用アルコールを吹きつけながら
乾いたぞうきんで畳の目に沿って拭きます。
最後によく乾燥させましょう。
3.クッションフロアに発生したカビ
丈夫で汚れに強いので
水回りなどによく使われるクッションフロア。
そんなクッションフロアにカビが発生して
しまったら…
カビ部分にアルコールを
広めにたっぷりと吹きつけ
水気が切れるまで少し待ちます。
中性洗剤を水で薄めた洗浄液で雑巾を固く絞り
その雑巾でカビを集めるようにして拭く。
カビを落とせたら
新しい雑巾をただの水で固く絞り
洗剤を残さないように拭き取ります。
水気を残すと滑るので乾拭きでしっかり水分を取って完了です。
アルコールの除菌で上手く落ちない場合は
漂白剤などを使ってみましょう。
まれに漂白剤を使って消毒しても
黒ずみが落ちないことがあります。
その場合はクッションフロアの
裏側からカビが出てきていることが
原因の場合があります。
クッションフロアの裏側に
湿気が溜まってカビが繁殖し
下の床材なども傷んでいる可能性が高いので
早めに対処する必要があります。
家庭でなんとかするのはかなりむずかしいので
業者に問い合わせて見てもらうのが安心です。
いかがでしたでしょうか?
カビは放っておくと
どんどん増殖し、人体にも影響を
与えかねません。
発生した場合は速やかに
掃除し、二度とカビが発生しない
ようにしたいですね。
カビ除去・対策についての
お問い合わせはこちらから
2018.05.02
「5月病」への対策方法
こんにちは。
皆さん楽しいGWをお過ごしでしょうか?
5月は大型連休もあり忙しく過ごされる方も
多いかと思います。
5月によく話題になるのが
「5月病」
4月になり仕事や学校
転居などで環境が変わり
最初のうちは張り切っていたのに
5月の連休明け頃から
なんとなく気分が落ち込む
仕事などに集中できない
眠れないといったスランプ状態に陥るのが
いわゆる「五月病」です。
「5月病」から、うつ病に移行する
ケースも少なくないので
なるべく早い対処が必要です!
「5月病」の症状には下記のような症状が見られます。
・やる気がでない
・体がだるい
・思考力、集中力の低下
・ネガティブ思考になる
・頭痛、腹痛
・食欲低下
では5月病を防ぐには!?
1.会話でストレスを解消
同僚や同期
家族や友人などとの
コミュニケーションの機会を大切に。
悩みを話すことでストレス解消になります。
食事も1人で食べる
「孤食」はなるべく避け
リラックスできる時間を
増やすことにつなげていきたいものです。
2.栄養バランスの取れた食事
食事は一品で済ませるよりも
「主食・副菜・主菜」を組み合わせるよう
意識しましょう。
不規則な食生活、偏った食事内容は
脳内の栄養不足を招き
とりわけ感情をコントロールする
神経伝達物質「セロトニン」が
不足しがちです。
セロトニンは動物性タンパク質に
多く含まれる「トリプトファン」を原料に合成されます。
3.質の良い睡眠
睡眠は疲労回復に重要な役割を果たします
。睡眠の質を上げるために
「起床・就寝の生活リズムを整える」
「夕食は寝る2時間前まで、入浴は1時間前までに済ませる」
「寝る前にテレビやパソコンを見ない」
などの生活習慣を身に付けましょう。
4.オフの日の過ごし方
オフの日は自分の好きなことに時間を費やし
仕事のことは忘れましょう。
体を動かすこともストレス解消法の1つです
ウォーキングやサイクリングなどの
有酸素運動でも感情をコントロールする
神経伝達物質「セロトニン」の分泌が促されます。
「5月病」は厚生労働省により
精神疾患が高血圧などと並んで
5大疾病に組み入れられる時代です。
自分だけでなく
人と人とのつながりで健康を守っていきたいですね。
2018.04.25
新生活‼一人暮らしでも大丈夫~早起き編~
こんにちは。
4月から新生活を始められた方は
そろそろ慣れてきた頃ですね。
気温が暖かくなってくると
朝なかなか起きられない方も
多いのではないでしょうか?
本日は朝早起きするための方法をご紹介します。
1.「明日は〇時に起きる」と思いながら寝る
意識をすることって実はとても大切です。
意識をすることにより、体内時計が合わせやすくなります。
2.目覚まし時計を布団に入ったままでは取れない所に置く
目覚まし時計を止めるまでに
一度起きなければいけない必要があるので
無意識に目覚まし時計を止めてしまう方に
オススメの方法です。
3.少しだけカーテンを開けて置き、朝になると太陽の光が差し込むようにする
防犯上遮光カーテンをしている人が
多いと思いますが朝の太陽光が遮られていて
部屋が真っ暗なのも朝起きられない原因の
一つと言えるかもしれません。
夜にカーテンを開けて寝ると
カーテンの意味がないし
さすがに防犯上よくないので
開けておくのは、ほんのちょっとだけでいいです。
4.寝る前の30分はリラックスして過ごす
寝る前の30分はTVや携帯電話など
光を発するものを見るのを避けるのも
脳がリラックスした状態になり
睡眠の質が上がり、朝起きやすくなります。
いかがでしたでしょうか?
早起きするには規則正しい生活が一番ですが
慣れない新生活でなかなかそうはいかないもの。
朝なかなか起きられない方は
本日ご紹介した方法などを
是非試してみて下さい♪